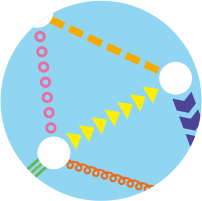- TOP
- 仕事を知る - プロジェクトストーリー
- #01 テクノロジーと共創で拓く農業プロジェクト
Project Story -仕事を知る
Project Story #01
「農業の新しいカタチ」を実践し、食の安定供給に挑む
テクノロジーと共創で拓く農業プロジェクト
担い手不足や気候変動など、農業を取り巻く環境は今、大きく変化しています。NTT東日本は2019年にNTTアグリテクノロジーを設立し、食の安定供給に向けた課題解決に取り組んできました。現場では、いま何が起きているのか──その取り組みをご紹介します。
Project Image

農業
- ・ 担い手不足や気候変動といった社会課題

先進テクノロジー
- ・ 次世代施設園芸による生産販売
- ・ 遠隔営農支援等のデータ駆動型農業
- ・ 陸上養殖プラントエンジニアリング

地域活性化と経済循環
- ・ 食の安定供給
- ・ 農業を起点とした産業振興
Project Member
-

2018年度入社蓮沼 祐紀
ビジネス開発本部
営業戦略推進部
営業戦略推進担当(一次産業G)入社後は東京エリアでセールス業務を経験、
NTT東日本の公募制度を利用し現職へ。
現在は東京都をはじめとした自治体や民間事業者に向けた
遠隔営農支援事業に従事。 -

2022年度入社富松 亮太
ビジネス開発本部
営業戦略推進部
営業戦略推進担当(一次産業G)学生時代から地域貢献への関心が高く、
入社時より営業戦略推進部にて新規事業に携わる。
現在は台湾での遠隔営農支援事業を中心とした、
データ駆動型農業ソリューションの企画、提案業務に従事。 -

2012年度入社黒木 惣太
ビジネス開発本部
営業戦略推進部
営業戦略推進担当(一次産業G)セールス業務を経験後、トレーニー制度を活用しベトナムへ。
帰国後、NTT東日本の収益拡大に貢献したい想いから新規事業を志向。
マネージャーとして一次産業分野の中期戦略事業立上げ業務に従事。
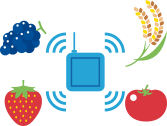 Project Interview
Project Interview
─本日はNTT東日本で、NTTアグリテクノロジーと連携しながら働いているお三方にお越しいただきました。様々な事業に挑戦されていると伺っておりますが、現在の事業内容について改めて教えてください。
黒木 : NTT東日本は、地域の方々から「農業にもICTの力を活かすことができないか」との声が数多く寄せられたことを真摯に受けとめ、地域の基幹産業である一次産業への本格的なアプローチが必要と判断し、2019年にNTTアグリテクノロジーを設立しました。設立当初は、次世代施設園芸による生産販売や顧客向け設計・施工、パートナー企業や地域の自治体と協力したデータ駆動型農業(遠隔営農支援等)の推進などからスタートしました。現在は、これまでの事業ドメインをベースとして、陸上養殖プラントエンジニアリング、加工食品の開発・販売等、一次産業の“これから”を見据えた事業を幅広く展開しています。こうした取り組みを通じて、地域や現場に寄り添いながら、一歩一歩、新たな価値の創出に取り組んでいるところです。
─様々な事業に取り組まれているのですね。
その中でも遠隔営農支援の分野で国内・海外のプロジェクトに取り組んでいるお二方に来ていただいています。
─そもそも遠隔営農支援とはどういった事業なのでしょうか?
蓮沼 :
遠隔営農支援とは、スマートグラスや環境センサー、ロボットなどを活用し、栽培の専門家が現地に赴かずとも、環境や作物の状況に応じて遠隔地から適切な営農指導を行える仕組みです。現場の生産者と、離れた場所にいる専門家をつなぐ“懸け橋”のような役割を果たします。
昨今、農業では担い手不足が深刻化していますが、それは生産者に限らず、営農指導を行う専門家も同様です。限られた専門家がすべての現場を頻繁に訪問することは現実的ではなく、特に新規就農者にとっては、すぐに頼れる相談相手が身近にいないことも大きな不安要素です。こうした現状を踏まえ、ICTを活用した遠隔による営農支援と、現地での直接的なサポートを組み合わせることで、専門家の知見をより多くの現場に届けることが可能になります。現場は必要なサポートを柔軟に受けながら栽培に取り組むことができ、こうした取り組みは新規就農者の増加や栽培技術継承の加速にもつながります。
私は現在、東京都内を中心にこの仕組みの実証を進めています。最初は「東京にもこんなに農地があるんだ」と驚きましたが、実は都内にも地域の産業として農業が根付いている場所が数多くあります。各地で抱えている課題は異なりますが、共通しているのは「専門家の頻繁な現地往訪が難しい」という点であり、遠隔営農支援が果たす役割は大きいと感じています。
社会に浸透させていく検証の中では、どのような課題がありますか?
蓮沼 :
現場の方から多く寄せられたのは、「専門機器の操作が不安」という声でした。私たちにとっては慣れた操作でも、農業の現場ではそうとは限りません。そこで私たちは、技術的な説明ではなく、実際の作業の中で機器を一緒に使いながら、体験を通じて「これなら使えるかも」と感じてもらえるよう心がけています。たとえば、スマートグラスを装着し、遠隔からどのような指示が届くかをその場で体験いただくことで、「これなら使えそうだ」と感じていただけるケースが増えてきました。
あわせて大切にしているのは、「これは自分たちの栽培に役立つ」と実感していただくことです。実際の収量や品質といった“成果”につながる仕組みであるとご納得いただけなければ、現場には根づきません。だからこそ、直接お話を伺い、その声をもとにシステムをカスタマイズしていく。現場のニーズに寄り添いながら、一緒に形をつくり上げていく過程や、実際に効果が出ている様子を見ると、本当にやりがいを感じますし、「次はどんなふうに役立ててもらえるかな」と考えるのが楽しみになりますね。

─同じく遠隔営農支援の分野で、富松さんは海外でのプロジェクトにも取り組んでらっしゃるとのことですね。
こちらはどういった取り組みなのでしょうか?
富松 : 現在、台湾の國立宜蘭大學やIT企業ThroughTek Co., Ltd.と連携し、台湾における遠隔営農支援の仕組みづくりに取り組んでいます。台湾でも日本と同様に、農業従事者の高齢化や担い手不足が課題となっており、こうした共通課題に対して、日本で蓄積してきた技術や現場経験をもとに、台湾の皆さんと共に解決策を模索しているところです。具体的には、遠隔営農支援の仕組みを活用して、栽培未経験者がメロンや地元特産のネギの栽培に挑戦し、それを専門家が離れた場所から営農指導する一連の取り組みです。現地の営農指導者とも連携しながら、台湾ならではの課題やニーズに合わせた遠隔営農支援のあり方を追求しており、“現場と共に育てる仕組み”の構築にこだわって取り組んでいます。ちなみに、私は元々別のプロジェクトを担当していたのですが、海外事業に強い関心があったため、社内で手を挙げてこの取り組みに参加させてもらいました!自ら思いを発信することでチャレンジの機会を得られるのも、NTT東日本ならではの特徴の一つだと感じています。
─プロジェクト特有の課題や、それに対して富松さんご自身が工夫されたことはありますか?
富松 :
やはり、言語や文化の違いから生まれる認識のズレに、最初少し戸惑いました。ただ、頻繁なオンラインコミュニケーションを重ねることで、少しずつ相互理解を深めていきました。多い時は週に何度も顔を合わせていたので、実際に初めて現地でお会いしたときは「ようやく直接会えた仲間」という、親しみのある感覚がありました(笑)。
そうした関係性を築けたからこそ、「このプロジェクトで何を実現したいのか」「どんな社会課題にどう向き合うのか」といった目的をしっかりと共有しながら、現地の関係者と一緒に仕組みそのものをデザインしていくプロセスが可能になったと感じています。またこれは国内外共通ですが、どんなに便利な技術や仕組みでも、現場の作業リズムに合っていなければ定着しません。だからこそ、現場の声に耳を傾けながら、一緒に“使いこなせる形”をつくっていくことを大切にしています。

台湾でのプロジェクトの様子
─農業分野という、一見するとNTT東日本の事業領域とは異なる分野での挑戦ですね。
蓮沼 : 通信業と農業は分野としては異なりますが、地域の皆さんと信頼関係を築きながらプロジェクトを動かしていくという点では、これまで私たちが通信インフラを通じて培ってきたノウハウがそのまま活きています。
富松 : 海外での取り組みでも、NTT東日本として築いてきた「地域に寄り添う姿勢」や丁寧なプロセスが評価されているのを感じます。相手国に対して一方的に技術を持ち込むのではなく、対話と共創を大切にしながら、お互いの知見を高め合うプロジェクトにしていきたいですね。
─ありがとうございました。
様々な変化を続けてきたNTT東日本グループの一次産業分野。今後のビジョンを教えてください。
黒木 : 食は誰にとっても身近で欠かせないものですが、近年は野菜や米の価格高騰、店頭での品薄といった事象を通じて、「当たり前に食べられる」ことの尊さが改めて注目されています。「食の安定供給」と「通信をつなぎ続ける使命」は、いずれも社会を支える重要な役割であるため、NTT東日本グループでは、農業をエッセンシャルなインフラのひとつと捉え、持続可能な形で次世代に繋げていくことを社会的責任と考えています。単なる栽培支援にとどまらず、生産から始まるサプライチェーンを一気通貫で支える体制を構築し、農業を起点とした産業振興を推進していきます。今後も、通信で培った技術と現場に根ざした共創を通じて、地域に根ざし社会を支える「農業の新しいカタチ」を実装していきたいと考えています。

─最後に、農業分野に想いを持つ学生に対してメッセージをお願いします。
黒木 :
農業の世界では、今まさに変革が始まっています。新たな視点やスキルを持った方が関わることで、現場はさらに進化していけると信じています。
実際に、農業だけに限らず、通信やデータ、エンジニアリング、経営企画など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが、現場に飛び込み、課題に向き合いながら活躍しています。私たちが大切にしているのは、“当事者意識を持って本気で一次産業に向き合う姿勢”です。ご自身の強みや関心を活かしながら、現場から変化を起こしていきたい──そんな想いを持った方と、一緒に未来をつくっていけることを、心から楽しみにしています!
Another Story
- ※掲載内容は取材当時のものです