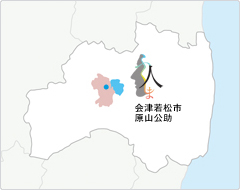会津木綿織元 原山公助

会津の気候風土と歴史を織り込む会津木綿400年の伝統
今から400年程前の天正年間(1573〜1592年)、時の会津藩主蒲生氏郷(がもううじさと)による城下町の整備と産業振興により、会津地方で綿花の栽培が始められ、旧領から織師を招いて織の技術を伝えたのが会津木綿の始まりとされています。また、会津は藍の栽培に適し、農民に限らず藩士の妻女の内職としても機織が奨励され、漆器などと並んで藩の保護下となり会津木綿が発展しました。
古くから会津地方では、モンペやサルッパカマなど、丈夫で肌合いが良く、冬の寒さや盆地の夏の暑さの気候風土に適し、保温性や吸汗性に優れた、日常生活に欠かせない生活布として会津木綿が使われてきました。
今回「ふくしま人」へご登場を頂いたのは、創業1899年(明治32年)株式会社原山織物工場「かねろく」6代目、原山公助(はらやまこうすけ)さん。会津地方で2軒だけになった会津木綿織元の原山織物工場の沿革から、まずお話しをお聞きしました。
「明治に入って日本で起こった産業革命により、製糸や綿紡績などの軽工業で機械化が進められましたが、1897年(明治30年)豊田佐吉によって自動織機が発明されると、それが日本中に普及されました。弊社も1899年(明治32年)の創業来、小幅(こはば・約37センチ)会津木綿の生地を作ってきました。明治末から大正にかけて生産の最盛期を迎えましたが、戦時中に制定された金属類回収令によって、使われていた織機の鉄材が供出され、織元が半減しました。戦後、買い直しされましたが、会津若松市に4軒、会津坂下町と塩川町にそれぞれ3軒、猪苗代町に2軒、その後、需要の減少や時代の趨勢(すうせい)によって生産縮小を余儀なくされ、現在では2軒のみとなりました。」
会津木綿は西日本と比べて、冬の厳しい寒さもあって多少厚目の生地に作られ、素朴な伝統が伝える美しい縞柄(しまがら)が特長で、創業当時から大切に守られ、受け継がれてきた縞柄の他にも、時代ごとに新しい柄が作り加えられ、現在までに100を越える縞柄の意匠があると原山さんは話します。
「会津木綿の縞柄は多種多様にありますが、昔は地域ごとに特有の縞柄があり、例えば猪苗代地域特有の猪苗代茶棒縞など、着用している縞柄で出身地域が分かったといわれています。」
それぞれの土地で育てた綿で糸を紡ぎ、その土地の藍で染め上げた様々な濃淡の糸を作り、“地縞(じじま)”と呼ばれる多彩な種類の縞模様は、ビビッドで鮮やかな染色が可能になった現在でも、会津木綿といえばすっと筋が通った柄で、頑固ながら一本筋の通った会津人の人柄を思わせる純朴な美しさが魅力です。